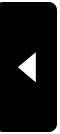自転車と法律と最近の目立つ施策
皆様いかがお過ごしですか。
昨日はお子様たちとお多賀さんに娘の七五三参りでした…。

いろいろ調べて自転車と法律に関してまとめてみました。
時間がないのと、書きすぎると見苦しいのでまた今度にしたいのですが、
さらに「自転車道」と「自転車通行帯」などについても調べたいです・・・。
さらに「自転車通勤の奨励策」についても調べたものもまとめたいです・・・。
主に参考にした本は「成功する自転車まちづくり 古倉宗治 学芸出版」です。
以下よろしければご参照ください。
************************************************
1960年 道路交通法の改正により「自転車は車両」と規定。
1970年 「自転車道の整備などに関する法律」により自転車道が規定される。
1970年 「道路構造令」により自転車道または自転車歩行車道が規定される。
※自転車を自動車交通から分離する方向が示される。
1978年 道路交通法の改正により道路標識などにより指示された場所において「普通自転車が歩道通行可」となる。
※その後長きにわたり道路における自転車の立場が曖昧となり混乱を招く。
1980年 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
※駐輪場の整備と違法駐輪の撤去と処分に関して、自治体の懸案事項の解決方法が取り決めらる。
1990年代と2000年代には数々の社会実験や自転車モデルとしの指定などの自転車奨励策が実施される。ハード中心に自転車走行空間の整備も行われる。賛否両論あるが、経験がその後の判断に生かされたのではないかと思われる。
自転車利用環境整備モデル地区
自転車通行環境整備モデル地区
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000190.html
自転車重点都市
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082301000332.html
自転車利用環境整備ガイドブック
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/06/061005/03.pdf
自転車走行空間の設計のポイント
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2010report/2010nilim41.pdf
2011年 警察庁通達「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」
※今一度「自転車は車両」であることを徹底することとし、自転車は基本的に車道左側を促し(やむを得ない場合のみ許可された歩道を走る)、その他、自転車利用環境の整備、教育とPRの実施、街頭指導取締の実施などを述べる画期的な通達。
ちなみにhttp://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku9/pdf/summary.pdf
■第9次交通安全基本計画(内閣府:平成23年度から27年度までの5年間)
においても、以下のように触れられております。
<道路交通の交通安全についての対策>
(高齢者・子どもの安全確保)
(歩行者・自転車の安全確保)
(生活道路・幹線道路における安全確保)
・歩行者の交通事故死者割合高く、3割を超える…自動車と比較して弱い立場にある歩行者の安全を確保する。
・通学路,生活道路,市街地の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を積極的に進め,歩行者の安全確保を図る。
・自転車乗用中の死者数の構成率が高い…自転車は被害者と加害者という両方の立場から、それぞれの対策を講じる。
・生活道路や市街地の幹線道路において、自動車や歩行者と自転車利用者の共存を図る。自転車の走行空間の確保を積極的に進める。
・自転車利用者にルールやマナーに違反する行動が多いことから,交通安全教育等の充実を図る。
・生活道路において自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備,交通指導取締りの強化等の対策を講じる。
・幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための対策等を推進するなど、総合的な対策を一層推進する。
※日本独自の展開として、「自転車の利用促進という観点」よりも「交通安全の徹底」という観点から、自転車走行空間の確保や交通安全教育などのソフト施策が盛り込まれていくというのが、面白いカタチだと思いました。何はともあれ、適切な自転車利用促進に向けて、一歩一歩前進している様子がまざまざと見られて、この時代に生きる幸せを感じる次第でございます・・・。
************************************************
以上以外にも自転車社会学会の「自転車から見た道路交通法」は参考になりました。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/index.html
長々と書きましたが以上です。
昨日はお子様たちとお多賀さんに娘の七五三参りでした…。

いろいろ調べて自転車と法律に関してまとめてみました。
時間がないのと、書きすぎると見苦しいのでまた今度にしたいのですが、
さらに「自転車道」と「自転車通行帯」などについても調べたいです・・・。
さらに「自転車通勤の奨励策」についても調べたものもまとめたいです・・・。
主に参考にした本は「成功する自転車まちづくり 古倉宗治 学芸出版」です。
以下よろしければご参照ください。
************************************************
1960年 道路交通法の改正により「自転車は車両」と規定。
1970年 「自転車道の整備などに関する法律」により自転車道が規定される。
1970年 「道路構造令」により自転車道または自転車歩行車道が規定される。
※自転車を自動車交通から分離する方向が示される。
1978年 道路交通法の改正により道路標識などにより指示された場所において「普通自転車が歩道通行可」となる。
※その後長きにわたり道路における自転車の立場が曖昧となり混乱を招く。
1980年 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
※駐輪場の整備と違法駐輪の撤去と処分に関して、自治体の懸案事項の解決方法が取り決めらる。
1990年代と2000年代には数々の社会実験や自転車モデルとしの指定などの自転車奨励策が実施される。ハード中心に自転車走行空間の整備も行われる。賛否両論あるが、経験がその後の判断に生かされたのではないかと思われる。
自転車利用環境整備モデル地区
自転車通行環境整備モデル地区
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000190.html
自転車重点都市
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082301000332.html
自転車利用環境整備ガイドブック
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/06/061005/03.pdf
自転車走行空間の設計のポイント
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2010report/2010nilim41.pdf
2011年 警察庁通達「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」
※今一度「自転車は車両」であることを徹底することとし、自転車は基本的に車道左側を促し(やむを得ない場合のみ許可された歩道を走る)、その他、自転車利用環境の整備、教育とPRの実施、街頭指導取締の実施などを述べる画期的な通達。
ちなみにhttp://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku9/pdf/summary.pdf
■第9次交通安全基本計画(内閣府:平成23年度から27年度までの5年間)
においても、以下のように触れられております。
<道路交通の交通安全についての対策>
(高齢者・子どもの安全確保)
(歩行者・自転車の安全確保)
(生活道路・幹線道路における安全確保)
・歩行者の交通事故死者割合高く、3割を超える…自動車と比較して弱い立場にある歩行者の安全を確保する。
・通学路,生活道路,市街地の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を積極的に進め,歩行者の安全確保を図る。
・自転車乗用中の死者数の構成率が高い…自転車は被害者と加害者という両方の立場から、それぞれの対策を講じる。
・生活道路や市街地の幹線道路において、自動車や歩行者と自転車利用者の共存を図る。自転車の走行空間の確保を積極的に進める。
・自転車利用者にルールやマナーに違反する行動が多いことから,交通安全教育等の充実を図る。
・生活道路において自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備,交通指導取締りの強化等の対策を講じる。
・幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための対策等を推進するなど、総合的な対策を一層推進する。
※日本独自の展開として、「自転車の利用促進という観点」よりも「交通安全の徹底」という観点から、自転車走行空間の確保や交通安全教育などのソフト施策が盛り込まれていくというのが、面白いカタチだと思いました。何はともあれ、適切な自転車利用促進に向けて、一歩一歩前進している様子がまざまざと見られて、この時代に生きる幸せを感じる次第でございます・・・。
************************************************
以上以外にも自転車社会学会の「自転車から見た道路交通法」は参考になりました。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/index.html
長々と書きましたが以上です。
Posted by
eco&rikisha
at
03:21
│Comments(
0
)
自転車は歩道以外を走行するのが適切か?確認してみる。
先日も商店街の歩道で、知り合いのお母さんというかおばあさんが自転車とぶつかって怪我をされた。気の毒なことである。自分も最近タイプは違うが事故を起こして大いに反省している最中である…。ちょうど話題にもなっているし、関連する会合の場でも議論のネタになっているので、本やネットを調べてみる。
☆警察庁より「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」通達が出た。
http://www.npa.go.jp/
・自転車のルール破りやマナーの悪さが目に付く昨今、
・考え方として「基本自転車は歩道以外(車道など)を走る」、
・考え方として「仕方がなく歩道を走る場合は歩行者優先」という観点に立ち、
・具体的方策としては「自転車通行可の歩道の見直し」、
・具体的方策としては「自転車は車両というルール周知・教育の実施」、
・具体的方策としては「指導取締りの強化」、
・具体的方策としては「都道府県警察による総合計画の策定」まで踏み込んでいる。
・この通達は落とし込みどころもしっかりされていて、事故を減らす有効な方策となりうる、ありがたい内容である。
・事故事例なども十分検討された結果だと思われるので、以下、確かに自転車は歩道以外を走る選択がベストであるという根拠を集めてみる。
★外出時交通分担率 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6370.html
・日本での自転車の分担率(15%)に対し
★交通事故の状況 http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
・H22年度における交通事故全体における自転車事故の割合は20.9%
・H22年度における交通事故死傷者全体における自転車事故死傷者の割合は16.8%となり、自転車が事故の原因となる割合は実際の交通の分担率からすると少し高い。
★自転車事故の原因とその状況
・交差点やそれに類する場所での事故が80.9%(出会い頭56.1%+右左折24.8%)
・自転車以外の交通事故で交差点でおこる割合は約4割
・自転車事故の相手はクルマである事故が84.0%となり、
・圧倒的に自転車は交差点でクルマとぶつかるということが多い。
・また、加害者・被害者ともに交通法規を守らない場合に事故になる場合が多い。
★車道の左端走行の危険性の低さ
http://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h22/pdf/houkoku/5-2-1.pdf
(その他参考文献:成功する自転車まちづくり 古倉宗治著P118)
・交差点に歩道以外(車道の左端)を走行して進入した場合の事故発生率は低い。
・逆に歩道走行(順走行・逆走行)の場合、明らかに事故発生率は高い。
以上から、自転車事故は他の交通手段と比べて少し多いが、事故原因は交差点周辺に偏っていて、その点において歩道上の自転車通行を減らせば、自転車が被害者となったり加害者となる事故は減らせるという傾向が見えてくる。通達にあるように、歩道以外に自転車走行が増えるとなると、周知とできる限りの対策が重要となる。合わせた実施が今後されることとなるのであろうが、自らはルール遵守に勤め、経緯をよく見て行きたいと思う。
☆警察庁より「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」通達が出た。
http://www.npa.go.jp/
・自転車のルール破りやマナーの悪さが目に付く昨今、
・考え方として「基本自転車は歩道以外(車道など)を走る」、
・考え方として「仕方がなく歩道を走る場合は歩行者優先」という観点に立ち、
・具体的方策としては「自転車通行可の歩道の見直し」、
・具体的方策としては「自転車は車両というルール周知・教育の実施」、
・具体的方策としては「指導取締りの強化」、
・具体的方策としては「都道府県警察による総合計画の策定」まで踏み込んでいる。
・この通達は落とし込みどころもしっかりされていて、事故を減らす有効な方策となりうる、ありがたい内容である。
・事故事例なども十分検討された結果だと思われるので、以下、確かに自転車は歩道以外を走る選択がベストであるという根拠を集めてみる。
★外出時交通分担率 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6370.html
・日本での自転車の分担率(15%)に対し
★交通事故の状況 http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
・H22年度における交通事故全体における自転車事故の割合は20.9%
・H22年度における交通事故死傷者全体における自転車事故死傷者の割合は16.8%となり、自転車が事故の原因となる割合は実際の交通の分担率からすると少し高い。
★自転車事故の原因とその状況
・交差点やそれに類する場所での事故が80.9%(出会い頭56.1%+右左折24.8%)
・自転車以外の交通事故で交差点でおこる割合は約4割
・自転車事故の相手はクルマである事故が84.0%となり、
・圧倒的に自転車は交差点でクルマとぶつかるということが多い。
・また、加害者・被害者ともに交通法規を守らない場合に事故になる場合が多い。
★車道の左端走行の危険性の低さ
http://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h22/pdf/houkoku/5-2-1.pdf
(その他参考文献:成功する自転車まちづくり 古倉宗治著P118)
・交差点に歩道以外(車道の左端)を走行して進入した場合の事故発生率は低い。
・逆に歩道走行(順走行・逆走行)の場合、明らかに事故発生率は高い。
以上から、自転車事故は他の交通手段と比べて少し多いが、事故原因は交差点周辺に偏っていて、その点において歩道上の自転車通行を減らせば、自転車が被害者となったり加害者となる事故は減らせるという傾向が見えてくる。通達にあるように、歩道以外に自転車走行が増えるとなると、周知とできる限りの対策が重要となる。合わせた実施が今後されることとなるのであろうが、自らはルール遵守に勤め、経緯をよく見て行きたいと思う。
Posted by
eco&rikisha
at
10:51
│Comments(
0
)
サイクリングの予定10/30と11/6
走行区分が話題となっている自転車ですが、田舎道ではそのほとんどが歩道もない道です。自転車は車道左側を通るのが原則で、左側を走行すれば田舎の国道や県道など交通量が多いところでも大丈夫なのですが、初心者の方と一緒に走る場合は走りやすい交通量が少ない道を選ぶことになります。それももちろん歩道もない道になるのですが、交通量が少ない道はゆったりとした時間が流れ、のどかな風景もあり、いいサイクリングルートになったりします。
10/30(日)愛知川駅出発にて「湖東遊ランサイクリング」と銘打った近隣のサイクリングの予定です。8:30集合9:00出発にて1時間ほど(申し込み不要にて直接駅前に集合)、よろしければご参加下さい。ちなみに同日愛荘町内のラポール秦荘では、自転車発電機などを用いた体験型自転車啓発イベントも実施します。話題の「自転車は歩道以外を走りましょう」という展示も実施予定です。
11/6(日)大津港出発にて南湖一周を行います。抱きしめてびわ湖のイベントにあわせ関連のイベントも巡りつつ回るサイクリングです。こちらは申し込みが必要です。http://gokan-seikatsu.jp/upfile/2276-2.pdf 湖岸道路はほとんどが歩道がありますが、今回特にイベントにて歩行者が多いことも想定されますので、ゆっくりと走らない自転車の性能どおりの走りをされる方には車道走行おすすめする予定です。
ご興味ある方はご参加よろしくお願いします。

写真はまったく関係ないのですが秋空がきれいでしたので…。先日の環境ビジネスメッセの様子です。
10/30(日)愛知川駅出発にて「湖東遊ランサイクリング」と銘打った近隣のサイクリングの予定です。8:30集合9:00出発にて1時間ほど(申し込み不要にて直接駅前に集合)、よろしければご参加下さい。ちなみに同日愛荘町内のラポール秦荘では、自転車発電機などを用いた体験型自転車啓発イベントも実施します。話題の「自転車は歩道以外を走りましょう」という展示も実施予定です。
11/6(日)大津港出発にて南湖一周を行います。抱きしめてびわ湖のイベントにあわせ関連のイベントも巡りつつ回るサイクリングです。こちらは申し込みが必要です。http://gokan-seikatsu.jp/upfile/2276-2.pdf 湖岸道路はほとんどが歩道がありますが、今回特にイベントにて歩行者が多いことも想定されますので、ゆっくりと走らない自転車の性能どおりの走りをされる方には車道走行おすすめする予定です。
ご興味ある方はご参加よろしくお願いします。

写真はまったく関係ないのですが秋空がきれいでしたので…。先日の環境ビジネスメッセの様子です。
自転車の利用促進と交通安全のデータ
「自転車利用促進と安全」という観点で、参考になるデータをインターネットで確認できるところからいくつか拾い上げてみました。気がついた点と感想も付けてみました。家族や知人にすすめるにあたり、他と比べても安全なのか?という疑問にはなかなか答えられずにいたので、今回調べてみて少し安心しました。そもそも、日本はそこそこ利用が多い。そこそこ危険でそこそこ安全。しかし交通法規を守らない走り方をしていると事故で死ぬ確率も高くなる・・・。なかなか味わい深い結果でした。写真はあまり関係ないですがサイクルトレーラーと娘と近所の道です。本日は米30kgと娘を一緒に運びました。重いものを運んでいるとますます感じますね・・・きまりを守って走るのが大切(安全)です。

★外出時交通分担率 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6370.html
・日本も自転車の分担率が他国と比べると比較的高い(15%)
・オランダが突出して自転車の分担率が高い(クルマの分担率が低いわけではない)
・クルマの分担率の低さで見るとノルウェーとスイスが低い(注目すべき!)
<感想>クルマの利用を控えるという観点からは、ノルウェーのクルマの分担率の低さに学ぶべきところがあるように思われた。この国は徒歩の分担率が突出して高く、公共交通機関の分担率はさして高くないところを見ると、歩いていけるところで用が足りる、すばらしい地域づくりがされているのか・・・!?と思わされる。もちろんオランダにも学ぶべきところが多いように感じた。オランダの自転車利用分担率の高さは、そもそも「クルマの利用を減らし」、「生活の質の向上を目指す」という計画(1990「第二次交通体系計画」、1991「自転車基本計画」)があったからで、計画が実を結んでいると言えると思う。
★自転車交通分担率と自転車交通事故死者数構成比率
http://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h22/pdf/houkoku/3-1.pdf
・日本は自転車の交通分担率も事故死構成比率もともに高い。
(他の交通手段利用に比べて、自転車はことさら安全とも危険ともいえない)
(あえて言うと、クルマはたくさん乗ってる割には事故死は少ない・・・自分が死なずに殺すほう)
(あえて言うと、歩行者はたくさん歩いている以上に事故死が多い・・・殺されるほう)
※1999年交通分担率 クルマ43%、徒歩21%、自転車15%、公共交通機関16%
※平成22年度事故死比率 クルマ32.9%、徒歩35%、自転車13.5%
・自転車の交通分担率が高いオランダやデンマークは、交通事故はその割には高くない。
<感想>自転車の交通分担率が高い割には支社が少ないオランダやデンマークは計画的に道や安全教育がなされているのであれば、参考にすべきところが多いように思われた。
★交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締状況につて(平成22年度)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001070077
・1970年には年間1.5万人を越え、1975~1995年まで年間1万人程度だった年間死者数が、2009年五十数年ぶりに5千人を割ったのはすばらしいことだと思う。ここ数年急激に減っている。
・割合はクルマ32.9%、徒歩35%、自転車13.5%にて、クルマの割合が近年減ってきている。
・気になるのは高齢者が半数以上ということ。
・気になるのは交通法規を守らなかったがために死なせたり、死んでしまう人が多いという現実。
<感想>高齢者を中心に、子どもから大人の各集団に向けて、的確な安全指導(安全教育)が必要であると感じた。特に利用が増えてきている(利用を増やしたい!)自転車においては、小中高の各段階向けと、職場向け、老人向けの利用促進を兼ねた安全教育が絶対条件と思われる。安全教育の実施に向けた施策なく利用の拡大を招けば、確実に事故の増大を招き、批判の対象となる(すでに一部で起きている事象)。
また、気になる書籍やHPからデータやまとめを探してみます。
いい書籍やHP,またおもしろいデータがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

★外出時交通分担率 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6370.html
・日本も自転車の分担率が他国と比べると比較的高い(15%)
・オランダが突出して自転車の分担率が高い(クルマの分担率が低いわけではない)
・クルマの分担率の低さで見るとノルウェーとスイスが低い(注目すべき!)
<感想>クルマの利用を控えるという観点からは、ノルウェーのクルマの分担率の低さに学ぶべきところがあるように思われた。この国は徒歩の分担率が突出して高く、公共交通機関の分担率はさして高くないところを見ると、歩いていけるところで用が足りる、すばらしい地域づくりがされているのか・・・!?と思わされる。もちろんオランダにも学ぶべきところが多いように感じた。オランダの自転車利用分担率の高さは、そもそも「クルマの利用を減らし」、「生活の質の向上を目指す」という計画(1990「第二次交通体系計画」、1991「自転車基本計画」)があったからで、計画が実を結んでいると言えると思う。
★自転車交通分担率と自転車交通事故死者数構成比率
http://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h22/pdf/houkoku/3-1.pdf
・日本は自転車の交通分担率も事故死構成比率もともに高い。
(他の交通手段利用に比べて、自転車はことさら安全とも危険ともいえない)
(あえて言うと、クルマはたくさん乗ってる割には事故死は少ない・・・自分が死なずに殺すほう)
(あえて言うと、歩行者はたくさん歩いている以上に事故死が多い・・・殺されるほう)
※1999年交通分担率 クルマ43%、徒歩21%、自転車15%、公共交通機関16%
※平成22年度事故死比率 クルマ32.9%、徒歩35%、自転車13.5%
・自転車の交通分担率が高いオランダやデンマークは、交通事故はその割には高くない。
<感想>自転車の交通分担率が高い割には支社が少ないオランダやデンマークは計画的に道や安全教育がなされているのであれば、参考にすべきところが多いように思われた。
★交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締状況につて(平成22年度)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001070077
・1970年には年間1.5万人を越え、1975~1995年まで年間1万人程度だった年間死者数が、2009年五十数年ぶりに5千人を割ったのはすばらしいことだと思う。ここ数年急激に減っている。
・割合はクルマ32.9%、徒歩35%、自転車13.5%にて、クルマの割合が近年減ってきている。
・気になるのは高齢者が半数以上ということ。
・気になるのは交通法規を守らなかったがために死なせたり、死んでしまう人が多いという現実。
<感想>高齢者を中心に、子どもから大人の各集団に向けて、的確な安全指導(安全教育)が必要であると感じた。特に利用が増えてきている(利用を増やしたい!)自転車においては、小中高の各段階向けと、職場向け、老人向けの利用促進を兼ねた安全教育が絶対条件と思われる。安全教育の実施に向けた施策なく利用の拡大を招けば、確実に事故の増大を招き、批判の対象となる(すでに一部で起きている事象)。
また、気になる書籍やHPからデータやまとめを探してみます。
いい書籍やHP,またおもしろいデータがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
自転車とまちづくりの本から考える
土曜日は運動会があり、子どもと触れ合う機会が嬉しかった。自転車タクシーの利用やレンタルなどの利用も多く仕事は忙しいが、まちづくりと自転車に今興味が沸いて情報に対する飢えと渇きがあるので、本で癒してみる・・・。
久しぶりに「自転車とまちづくり」(渡辺千賀恵著1999年学芸出版)を読み返す(よくまとめておられるいい本です)。データはインターネットで最新のものも見比べながらみると味わい深い。2つのうねりとして、1970年代半ばの石油ショックと、1997年の地球温暖化防止国際会議あたりからの6%削減の機運より、自転車を利用しようという積極論が存在する。しかしながら、戦後増え続けた(年間100万台程度)自転車が石油ショック以降急激に増加し、バスの割高費も同じくして高くなったことなどからも駅前や商店街での駐輪問題が激化し、自転車を抑制しようという動きも存在する。
一方、他国では日本同様に石油ショック以降増え続ける自転車利用があるが、オランダなど、きちんと社会システムに組み込む計画と法整備が見られる点を紹介し、日本においては横断的テーマとして認識し多面的連携とリーダーシップのもとに、散在している関心をひとつにして自転車とまちづくりに取り組むべきとまとめている。
他国(オランダの例)には増え続けるクルマによる問題解決のためと、生活の質を高める目的のために、「クルマ利用の増加を抑制しよう」という明確な目的がある。1990年に交通の便利さを維持しクルマ利用の増加を抑制する「第二次交通体系計画」が議会で承認され、翌年には交通土木省が「自転車基本計画」を立案し、「クルマから自転車、もしくは自転車+公共交通機関への転換」「道路の安全化」「盗難防止」などを謳う。この事例は非常に参考になる。
わが国ではまだ、都市問題や環境問題解決の手法としての自転車利用促進は、機運がまだ十分には高まっていないように思う。「生活の質を高める」という目的をさらに掘り下げて、「クルマ利用を前提とした世の中が作り上げてきたものの総括ととその問題解決手法の検討」「クルマ利用を前提としない、徒歩や自転車でいける範囲での生活の完結ということの検討-人同士の結びつきの強化」と考えた時、大きな問題の解決として、心の満足を伴った「生活の質の向上」が見込めるように思う。
心の満足といっても「仕事」があってのこと、他国との関係があってのことでもあるので、この本は「自転車にまつわるまちづくり」だけが関心ではあるが、次の本を読み継ぐ良いきっかけとなった。

久しぶりに「自転車とまちづくり」(渡辺千賀恵著1999年学芸出版)を読み返す(よくまとめておられるいい本です)。データはインターネットで最新のものも見比べながらみると味わい深い。2つのうねりとして、1970年代半ばの石油ショックと、1997年の地球温暖化防止国際会議あたりからの6%削減の機運より、自転車を利用しようという積極論が存在する。しかしながら、戦後増え続けた(年間100万台程度)自転車が石油ショック以降急激に増加し、バスの割高費も同じくして高くなったことなどからも駅前や商店街での駐輪問題が激化し、自転車を抑制しようという動きも存在する。
一方、他国では日本同様に石油ショック以降増え続ける自転車利用があるが、オランダなど、きちんと社会システムに組み込む計画と法整備が見られる点を紹介し、日本においては横断的テーマとして認識し多面的連携とリーダーシップのもとに、散在している関心をひとつにして自転車とまちづくりに取り組むべきとまとめている。
他国(オランダの例)には増え続けるクルマによる問題解決のためと、生活の質を高める目的のために、「クルマ利用の増加を抑制しよう」という明確な目的がある。1990年に交通の便利さを維持しクルマ利用の増加を抑制する「第二次交通体系計画」が議会で承認され、翌年には交通土木省が「自転車基本計画」を立案し、「クルマから自転車、もしくは自転車+公共交通機関への転換」「道路の安全化」「盗難防止」などを謳う。この事例は非常に参考になる。
わが国ではまだ、都市問題や環境問題解決の手法としての自転車利用促進は、機運がまだ十分には高まっていないように思う。「生活の質を高める」という目的をさらに掘り下げて、「クルマ利用を前提とした世の中が作り上げてきたものの総括ととその問題解決手法の検討」「クルマ利用を前提としない、徒歩や自転車でいける範囲での生活の完結ということの検討-人同士の結びつきの強化」と考えた時、大きな問題の解決として、心の満足を伴った「生活の質の向上」が見込めるように思う。
心の満足といっても「仕事」があってのこと、他国との関係があってのことでもあるので、この本は「自転車にまつわるまちづくり」だけが関心ではあるが、次の本を読み継ぐ良いきっかけとなった。